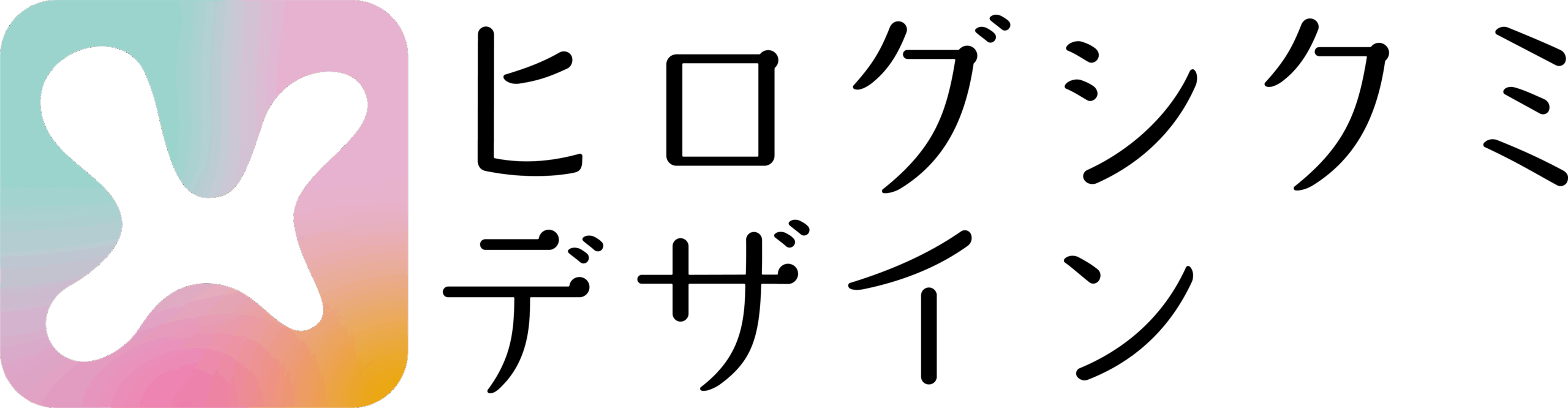ブログ
BLOG
GPT-5登場!これからAIもっと楽しくなる
特徴・進化点・「GPT-5 Thinking」の使い分けまで、やさしく解説

ついに出ましたGPT-5!
個人的にとても楽しみでした。
最近はAIを使わない日がないくらいお世話にになってるので、進化は大歓迎です。
その注目のAI、GPT-5がどのように進化したのかGPT-5に聞いてみましたw
親切に教えてくれたのでご紹介します。
1. GPT-5は何が新しいの?(まず結論)
GPT-5は、用途に合わせて“素早く答えるか”“深く考えるか”を自動で選べるAIです。
ChatGPTでは、通常は速いモデルが回答し、難しい質問や曖昧な依頼では「GPT-5 Thinking」という“よく考えるモード”に切り替わります。
これを裏側で判断するのがリアルタイム・ルーターという仕組み。
必要なら手動でThinkingを指定することもできます。
2. 具体的な進化:精度・速さ・コーディング・安全性
2-1. 事実の正確性がアップ(=“うっかり間違い”が減った)
OpenAIの発表によると、GPT-5はGPT-4oよりも事実誤りが約45%減少。
さらにThinkingを使うと、前世代の推論モデルo3より大幅にミスが減ります。
長文の事実確認や、曖昧な問いでも“無理に断定しない”挙動が強化されました。
2-2. コーディングが超強化(実務で刺さる)
実務系のプログラミング課題ベンチマークSWE-bench Verifiedで74.9%、コード編集タスクAider Polyglotで88%。
現場のツール連携や“段取り→実行→検証”のエージェント的作業も安定してこなします。
2-3. 数学・マルチモーダル・ヘルス分野でも上位
AIME 2025で94.6%、MMMU 84.2%、HealthBench Hard 46.2%など、幅広い分野でSOTA(当時最高水準)を記録。
医療情報については“医師に相談する前の理解を助けるパートナー”的な振る舞いが強化されました。
※医療判断は必ず専門家へ。
2-4. 速いのに無駄が少ない
Thinkingを使っても、前世代の推論モデルより少ないトークン量で高成績を出す設計。
つまり“よく考えるけどダラダラ長くない”方向へ調整されています。
3. 「GPT-5」と「GPT-5 Thinking」の違いと使い分け
ざっくりイメージ
•通常のGPT-5(速いほう):日常の質問、短い文章作成、要約、定型作業。反応が速く、十分に賢い。
•GPT-5 Thinking(よく考えるほう):複雑な判断や長い段取りが必要な仕事。曖昧な要求の整理、重要な意思決定の補助、長期の計画立案、コードの大規模修正などに向く。
使い分け早見表
•メールの下書き・短いコピー → 通常GPT-5
•要件が曖昧な企画の壁打ち → Thinking(最初に“前提を質問して”と書くと◎)
•長文の事実関係チェック → Thinking(“根拠URLも提示して”と依頼)
•サイト全体の設計や大規模コード修正 → Thinking(段取り→実行→検証まで)
•ブログのリライトや見出し案だし → 通常GPT-5→必要に応じてThinkingで深掘り
Thinkingの呼び出し方
•ChatGPTのモデル選択で「GPT-5 Thinking」を選ぶ
•プロンプトに「これについて深く考えて」など明示的に書く(ルーターが反応)
4. 仕事での活用アイデア(中小企業・スタートアップ向け)
ここに多くの方は期待しいるのではないでしょうか?
4-1. コンテンツ制作
•通常GPT-5:お知らせ・ブログの素案、要約、タイトル案、FAQたたき台
•Thinking:事例記事の骨子設計、競合との差別化ポイントの言語化、業界動向の要点整理(※根拠リンク提示を指示)
4-2. 営業・提案・資料作成
•通常:提案書の見出し作成、問い合わせ返信テンプレ
•Thinking:提案のロジック設計→反論対応案→見積り根拠の一貫生成(“漏れがないか検証して”と依頼)
4-3. Web制作・運用(ノーコード/ローコード含む)
•通常:画像ALTやメタ説明文、文言改善
•Thinking:サイト構成の棚卸し→改善ロードマップ→A/Bテスト計画、大規模コードの改修プランとパッチ提案(SWE-bench系が得意)
4-4. 経営の意思決定サポート
•Thinking:条件付きの損益試算や採用計画の前提整理、「情報が足りないときに何を確認すべきか」の質問リスト作成(=判断の漏れ防止)
5. はじめ方:どこで使える?どう選ぶ?
ChatGPTで使う(非エンジニア向け)
1.ChatGPTを開く → 既定がGPT-5
2.難しそうな依頼は、モデルを「GPT-5 Thinking」に切替 or 「深く考えて」と明示
3.Plusだと使える回数に余裕、Proだと「GPT-5 pro」(さらに長く深く考える版)が使える
APIや外部ツールで使う(エンジニア/ツール導入)
•APIではgpt-5 / gpt-5-mini / gpt-5-nanoの3サイズ。
速度・コスト・性能を状況に応じて選べます。
ChatGPTの“速いモデル”とは別物(開発者向けの調整)という点も公式に明言。
6. 注意点と限界(過信しないコツ)
•“万能ではない”のは引き続き同じ。
公開直後は、地名のスペルや知識の取り違えなど、初期の“つまずき”報告もあるため、重要な決定や公開情報は人のレビューを必ず挟みましょう。
•医療・法律など高リスク領域は、必ず専門家に確認し、AIの答えは“補助輪”と考えるのが安全です。
•Thinkingの使いすぎ=コスト/時間増の可能性があるため、通常→必要時にThinkingが基本。
7. まとめ:使い分けが最大の威力を引き出す
•通常GPT-5:速く・十分に賢い。日々の作業をサクサク前進。
•GPT-5 Thinking:難題・曖昧・長期・大規模は“深く考えて”確度を上げる。
•実務ポイント:まず通常 → 迷ったらThinking → 根拠を要求。この流れで“速さと質”を両取りできます。
いかがでしょか?
ChatGPTに出してもらった特徴で難しいところも多かったでしょう。
速度が上がったり、コーディング性能の向上はとても嬉しい。
そしてハルシネーションが減ったのはとても嬉しいですね。
これからガシガシ使って、良い使い方などわかってきたら、ご報告します。